「キャンプの醍醐味といえば、やっぱりキャンプ飯!」
そう思って色々調べてみるものの、外でご飯を炊くのって、なんだか難しそう…と感じていませんか?
- 「火加減の調整が大変そう…」
- 「焦がしてしまったり、芯が残ったりで失敗しそう…」
- 「そもそも、どんな道具を揃えればいいのか分からない…」
キャンプ初心者の方なら、誰もが一度は抱える悩みだと思います。私もキャンプを始めた頃は、飯ごうでご飯を炊くことに高いハードルを感じていました。
しかし、そんな悩みを一瞬で解決してくれる魔法のような方法があります。それが「メスティンを使った自動炊飯」です。
「自動」と聞くと、なんだか特別な機械が必要なように聞こえるかもしれませんが、そんなことはありません。使うのは、アルミ製の弁当箱のような見た目の「メスティン」と、100円ショップでも手に入る「固形燃料」だけ。
火加減の調整は一切不要。固形燃料に火をつけたら、あとは火が消えるまで”ほったらかし”にするだけで、まるで高級料亭で出てくるような、ふっくらツヤツヤの絶品ご飯が炊きあがるのです。
この記事では、キャンプ初心者の方でも絶対に失敗しない、メスティン自動炊飯のやり方を、準備から片付けまで、どこよりも詳しく、丁寧に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、あなたは「ご飯を炊くのが一番カンタン!」と自信を持って言えるようになっているはずです。さあ、一緒にキャンプで絶品ごはんを炊く感動を味わいましょう!
そもそも「メスティン」って何?キャンプで人気の理由
まずは、今回の主役である「メスティン」について少しだけお話しします。すでにご存知の方は、次の章へ進んでくださいね。
メスティンとは「万能クッカー」のこと
メスティン(Mestin)とは、スウェーデン発祥のアルミ製飯ごう(クッカー)のことです。元々はスウェーデン軍で使われていたものですが、その使い勝手の良さと無骨でシンプルなデザインから、今や世界中のキャンパーに愛されています。
長方形の弁当箱のような形状で、取っ手(ハンドル)が付いているのが特徴です。
なぜ、こんなにもキャンパーに人気なの?
メスティンがこれほどまでに支持されるのには、ちゃんとした理由があります。
- 熱伝導率が高く、調理が早い メスティンの素材であるアルミは、鉄やステンレスに比べて熱伝導率が非常に高いのが特徴です。つまり、火の熱が全体に素早く均一に伝わるため、ご飯が美味しく炊けるだけでなく、様々な料理の調理時間を短縮できます。
- 「炊く」以外もこなす万能性 メスティンはご飯を炊く(炊飯)だけの道具ではありません。「焼く」「煮る」「蒸す」「燻す(スモーク)」といった、あらゆる調理法に対応できます。パスタを茹でたり、アヒージョを作ったり、シュウマイを蒸したり…。メスティンが一つあれば、キャンプ飯のレパートリーが無限に広がります。
- 軽量で持ち運びやすい(パッキングしやすい) アルミ製なので非常に軽く、キャンプや登山への持ち運びも苦になりません。また、四角い形状はバックパックの隙間に収まりやすく(パッキングしやすい)、デッドスペースが生まれにくいのも嬉しいポイント。メスティンの中に、固形燃料やカトラリーなどの小物を収納することもできます。
- 所有欲を満たすデザイン性 機能性はもちろんですが、そのシンプルでミニマルなデザインも人気の理由の一つ。使い込むほどに味が出てくるアルミの風合いは、まるでギアを育てているような感覚になり、愛着が湧いてきます。
初心者のメスティン選び|サイズと加工で選ぼう
いざメスティンを買おうと思っても、様々なブランドから色々な種類が発売されていて、どれを選べばいいか迷ってしまいますよね。初心者が最初に選ぶべきポイントは「サイズ」と「フッ素加工の有無」です。
- サイズで選ぶ メスティンは主に「レギュラーサイズ」と「ラージサイズ」の2種類があります。
- レギュラーサイズ(1.5合炊き程度): ソロキャンプやデュオキャンプに最適。最も一般的で、レシピ本などもこのサイズを基準にしていることが多いです。初心者が最初に買うなら、まずはこのサイズがおすすめです。
- ラージサイズ(3~4合炊き程度): ファミリーキャンプやグループキャンプで活躍します。レギュラーサイズがすっぽり収まるものが多く、スタッキング(重ねて収納)できるのも便利です。
- フッ素加工(ノンスティック加工)の有無で選ぶ 最近では、内側にあらかじめフッ素加工が施されているメスティンも増えています。
- 加工あり: ご飯や食材がこびりつきにくく、後片付けが圧倒的に楽になります。特に炊き込みご飯や炒め物をする際に真価を発揮します。初心者の方や、洗い物を少しでも楽にしたい方には、加工ありのモデルを強くおすすめします。
- 加工なし: 昔ながらのシンプルなメスティンです。一手間かかる「シーズニング」という儀式が必要な場合がありますが、使い込むほどに味が出る経年変化を楽しみたい方にはこちらが人気です。
【知っておきたい】シーズニングって何? シーズニングとは、アルミ製品特有の臭いを取り除き、表面に膜を作ることで焦げ付きや黒ずみを防ぐために行う、購入後の初期作業のことです。米のとぎ汁でメスティンを煮るのが一般的な方法です。 最近の製品は精度が高く、シーズニング不要なものも増えていますが、一手間かけることで、より愛着が湧くのも事実。フッ素加工がないメスティンを購入した際は、ぜひ挑戦してみてください。
なぜ火加減不要?「自動炊飯」の仕組み
「火加減の調整がいらないなんて、信じられない…」 そう思うのも無理はありません。しかし、これにはちゃんとした科学的な理由があるのです。
メスティン自動炊飯の秘密は、「固形燃料が燃え尽きる時間」と「ご飯が炊きあがる時間」が、まるで計算されたかのようにピッタリ一致する点にあります。
一般的に、市販されているポケットストーブ用の固形燃料(25g~30g)は、約20分~25分で燃え尽きるように作られています。そして、メスティンで1合のご飯を炊くのに必要な加熱時間も、奇跡的に約20分~25分なのです。
つまり、 固形燃料に火をつける → 燃料がなくなるまで加熱 → 火が消えたら炊飯完了 という、非常にシンプルな方程式が成り立ちます。
キャンパーたちはこの特性を発見し、「これなら火の番をしなくても、ほったらかしで炊けるじゃないか!」と編み出されたのが、この「自動炊飯」というわけです。あなたはただ、火が消えるのをのんびり待っているだけでいいのです。
【完全ガイド】メスティン自動炊飯の6ステップ
お待たせしました!ここからは、実際にメスティンで自動炊飯を行う手順を、写真を交えながら6つのステップで徹底的に解説していきます。この通りにやれば、誰でも必ず美味しいご飯が炊けますので、安心してくださいね。
Step 0:準備するものリスト
まずは必要な道具を揃えましょう。どれもキャンプ用品店や、今では100円ショップ、ホームセンターでも手軽に手に入ります。
- メスティン(レギュラーサイズ): 今回は1合炊きで解説します。
- お米(1合): 計量カップがなくても大丈夫。後ほど裏技を紹介します。無洗米だとさらに楽ちんです。
- 水(約200ml): 水の量も、計量カップなしで測れます。
- ポケットストーブ(固形燃料用ゴトク): メスティンを安定させるための台。コンパクトに折りたためるものが便利です。
- 固形燃料(25g~30gのもの1個): このグラム数が自動炊飯の鍵です。旅館の夕食で出てくる、あの青い燃料です。
- ライターやマッチ: 火をつけるために必要です。柄の長いチャッカマンタイプが安全でおすすめ。
- タオルや保温ケース: 蒸らしの工程で使います。なくてもできますが、あると美味しさが格段にアップします。
- (あれば)耐熱シートやトレー: 地面やテーブルを熱から守るために敷きます。安全のために用意しましょう。
Step 1:お米を研いで、水を入れる
まずはお米を研ぎます。キャンプ場では環境に配慮し、炊事場で行いましょう。とぎ汁をそのまま地面に流すのはNGです。 この工程が面倒な方は、無洗米を使うのが断然おすすめです。時間も短縮でき、水の節約にもなります。
次にお米をメスティンに入れ、水を注ぎます。ここが最初の重要ポイントです!
【初心者向け裏技】
計量カップ不要!水の測り方 メスティンには、本体の側面に「リベット」と呼ばれる丸い鋲が2つ付いています。実は、このリベットのちょうど中心あたりまで水を入れると、おおよそ1合炊きに最適な水量(約200ml)になるように設計されているものが多いのです。(※メーカーによって個体差はあります)これさえ覚えておけば、計量カップを忘れても安心。キャンプでは荷物をいかに減らすかも重要なので、ぜひ活用してください。
Step 2:しっかり浸水させる(最重要工程!)
水を加えたら、蓋をしてお米に水を吸わせる「浸水」を行います。 実は、この浸水こそが、ご飯をふっくら美味しく炊き上げるための最も重要な工程と言っても過言ではありません。
なぜ浸水が必要かというと、お米の中心部までしっかりと水分を行き渡らせるためです。この工程をサボると、お米の芯が残ってしまい、ポソポソとした食感の残念なご飯になってしまいます。
浸水時間の目安は以下の通りです。
- 夏場:最低30分
- 冬場:最低1時間
気温が低い冬場は、お米が水を吸いにくくなるため、長めに時間を取るのが美味しく炊くコツです。この待ち時間を利用して、他の料理の準備をしたり、のんびりコーヒーを飲んだりして過ごしましょう。「美味しいご飯のためのおまじない」だと思って、じっくり待ってあげてください。
Step 3:ポケットストーブにセッティングする
浸水が終わったら、いよいよ炊飯の準備です。 安全な場所に耐熱シートを敷き、その上にポケットストーブを設置します。ポケットストーブの溝に固形燃料をはめ込み、その上に浸水させたメスティンを乗せます。
この時、メスティンがグラグラせず、安定していることをしっかり確認してください。風が強い日は、風防(ウインドスクリーン)があると、火が安定し、効率よく加熱できます。
【ワンポイント】蓋に重しを置こう 炊飯が始まると、中の蒸気圧で蓋が持ち上がり、カタカタと動くことがあります。吹きこぼれの原因にもなるため、蓋の上に石や缶詰などの重しを乗せておくのがおすすめです。これにより圧力がしっかりかかり、より美味しく炊きあがります。
Step 4:着火!あとは、ほったらかすだけ
準備が整ったら、ライターで固形燃料に着火します。 火がついたら、あなたの仕事はもう終わりです。ここからは火が消えるまで、ただひたすら“ほったらかし”。
火加減の調整は一切必要ありません。最初は静かですが、だんだんと「グツグツ…」という音と共に、湯気が立ち上ってきます。ご飯の炊けるいい香りが漂ってきて、食欲をそそられます。
この待ち時間は約20分~25分。焚き火を眺めたり、仲間とおしゃべりしたり、自由に過ごしましょう。この「何もしなくていい時間」こそ、自動炊飯の最大の魅力です。
Step 5:火が消えたら、ひっくり返して蒸らす
やがて固形燃料の火が自然に消えます。これで炊飯(加熱)の工程は完了です。 火傷に注意しながら、メスティンをポケットストーブから下ろします。
しかし、ここで焦って蓋を開けてはいけません。最後の仕上げ、「蒸らし」の工程が残っています。
蒸らしを行うことで、お米の水分が均一になり、ふっくらと甘みのあるご飯に仕上がります。
- メスティンをタオルで包む 用意しておいたタオルで、メスティン全体をくるみます。
- 逆さまにして置く タオルで包んだメスティンを、ひっくり返して(逆さまにして)地面に置きます。こうすることで、鍋底に溜まった余分な水分が全体に行き渡り、ご飯がベチャッとなるのを防げます。
- 10分~15分待つ この状態で10分から15分ほど、再び放置します。この最後の我慢が、美味しさを最大限に引き出します。
専用の保温ケース(メスティンポーチ)があると、保温性が高まり、さらに美味しく仕上がります。見た目もおしゃれなので、気分も上がりますよ。
Step 6:完成!感動のご対面
さあ、蒸らしの時間も終わりました。いよいよ、感動の瞬間です。 火傷に気をつけながらタオルを外し、ゆっくりと蓋を開けてみてください。
そこには、湯気と共に立ち上る炊きたてご飯の香り、一粒一粒がキラキラと輝き、ふっくらと立ったお米の姿があるはずです。
しゃもじで底からさっくりと混ぜ、お茶碗によそって、まずは一口。 自然の中で、自分で炊いたご飯の味は、どんな高級レストランの料理にも勝る、忘れられないご馳走になることでしょう。底にできた香ばしい「おこげ」も、メスティン炊飯ならではの楽しみの一つです。
【応用編】自動炊飯で絶品「炊き込みご飯」に挑戦!
基本の白米が完璧に炊けるようになったら、次は少しステップアップして「炊き込みご飯」に挑戦してみましょう。自動炊飯のやり方はそのままで、具材と調味料を加えるだけで、驚くほど簡単に豪華なキャンプ飯が完成します。
ここでは、コンビニやスーパーで手軽に揃う食材を使った、超簡単レシピを2つご紹介します。
レシピ1:焼き鳥缶で!悪魔の炊き込みご飯
【材料(1合分)】
- お米:1合
- 焼き鳥缶(タレ味):1缶
- 水:適量(リベットの中心まで)
- 醤油:小さじ1
- 刻みネギ、七味唐辛子:お好みで
【作り方】
- メスティンに研いだお米と、焼き鳥缶をタレごと全て入れる。
- 醤油を加え、リベットの中心まで水を入れる。(缶詰のタレも水分なので、少しだけ水を減らすのがコツ)
- 軽くかき混ぜて、蓋をする。
- **浸水(30分以上)**をしっかり行う。
- あとは基本の自動炊飯と同じ。固形燃料に火をつけ、火が消えたらひっくり返して15分蒸らす。
- 蒸らし終わったら、お好みで刻みネギや七味唐辛子を散らして完成!
缶詰の旨味がお米一粒一粒に染み渡り、箸が止まらなくなる美味しさです。
レシピ2:鮭ときのこのバター醤油ごはん
【材料(1合分)】
- お米:1合
- 鮭フレーク:大さじ2~3
- しめじ、舞茸など:お好みのきのこをひとつかみ
- 水:適量(リベットの中心まで)
- 白だし:大さじ1
- バター:10g
- 刻みネギ、黒胡椒:お好みで
【作り方】
- メスティンに研いだお米、鮭フレーク、手でほぐしたきのこを入れる。
- 白だしを加え、リベットの中心まで水を入れて軽く混ぜる。
- 浸水(30分以上)をしっかり行う。
- あとは基本の自動炊飯と同じ。固形燃料に火をつけ、火が消えたらひっくり返して蒸らす。
- 蒸らし終わった後、蓋を開けて熱々のうちにバターを乗せる。
- バターが溶けたら全体をさっくり混ぜ、お好みでネギや黒胡椒を振って完成!
バターのコクと醤油の香ばしい香り、きのこの旨味が口いっぱいに広がる、秋キャンプにもぴったりの一品です。
【Q&A】よくある失敗と解決策
誰でも成功する自動炊飯ですが、慣れないうちは小さなトラブルが起きることも。よくある失敗例とその解決策をまとめたので、困ったときは参考にしてください。
Q1. ご飯に芯が残ってしまいました… A1. 原因のほとんどは「浸水不足」か「水分量不足」です。
- 対策1:浸水時間を長くする。 特に気温の低い日は、最低でも1時間、できれば2時間ほど浸水させてみてください。
- 対策2:水の量を少しだけ増やす。 リベットの中心より、ほんの少し(1~2mm)多めに水を入れてみましょう。
Q2. 底が真っ黒に焦げ付いてしまいました! A2. 火力が強すぎたか、炊飯時間が長すぎた可能性があります。
- 対策1:固形燃料のグラム数を確認する。 1合炊きの場合、25gの固形燃料が最適です。30g以上のものだと火力が強く、焦げやすくなることがあります。
- 対策2:風のない場所で炊飯する。 強風に煽られると炎が大きくなり、焦げ付きの原因になります。風防を使うのが効果的です。
- 対策3:フッ素加工のメスティンを使う。 焦げ付きのストレスから解放されたいなら、これが一番の解決策です。
Q3. 盛大に吹きこぼれて、コンロ周りがベタベタに… A3. 水の量が多すぎたか、蓋がしっかり閉まっていなかったことが考えられます。
- 対策1:水の量を正確に測る。 リベットの中心、という基本をもう一度確認してみましょう。
- 対策2:蓋の上に重しを置く。 炊飯中に蓋が浮き上がらないように、石や缶詰などを乗せておくことで、吹きこぼれを大幅に防げます。
Q4. 100円ショップの固形燃料でも大丈夫ですか? A4. 全く問題ありません! 100円ショップで売られている固形燃料でも、25g前後のものであれば、問題なく自動炊飯ができます。3個入りで110円など、非常にコストパフォーマンスが高いので、初心者の方はまずはこちらから試してみるのがおすすめです。
大事な相棒を長く使うために|メスティンのお手入れ方法
美味しいご飯を作ってくれたメスティンは、感謝を込めてしっかりお手入れしてあげましょう。正しいお手入れが、メスティンを長く使うための秘訣です。
- 基本の洗い方 使用後は、柔らかいスポンジと中性洗剤で優しく洗います。スチールたわしやクレンザーは、表面を傷つけ、焦げ付きの原因になるので絶対に使わないでください。洗った後は、水分をしっかり拭き取り、よく乾燥させてから保管しましょう。
- 頑固な焦げ付きを落とすには? もし焦げ付かせてしまっても、諦めないでください。
- メスティンに焦げが浸るくらいの水を入れ、重曹を大さじ1杯ほど加える。
- 火にかけて沸騰させ、そのまま10分ほど煮る。
- 火から下ろし、冷めるまで放置する。
- 冷めたらお湯を捨て、スポンジでこすると、スルッと焦げが剥がれ落ちます。
この方法で、ほとんどの焦げは綺麗に落とすことができます。
まとめ:さあ、あなたも「メスティン自動炊飯」でキャンプ飯マスターに!
今回は、キャンプ初心者でも絶対に失敗しない「メスティン自動炊飯」の方法を、これでもかというほど詳しく解説してきました。
もう一度、簡単な流れをおさらいしましょう。
- 米を研いで、水と30分以上浸水させる
- ポケットストーブに固形燃料とメスティンをセットする
- 火をつけて、あとは“ほったらかし”
- 火が消えたら、タオルに包んでひっくり返し、15分蒸らす
たったこれだけで、誰が炊いても、いつでも、どこでも、感動するほど美味しいご飯が炊きあがります。
火加減を気にしなくていいので、炊飯している間に他の料理を作ったり、ゆっくり自然を眺めたりと、キャンプの時間をより有意義に使えるのも大きなメリットです。
この記事を片手に、ぜひ次のキャンプでメスティン自動炊飯に挑戦してみてください。青空の下で食べる、炊きたてのホカホカご飯の味は、きっとあなたのキャンプライフを、より一層豊かで素晴らしいものにしてくれるはずです。
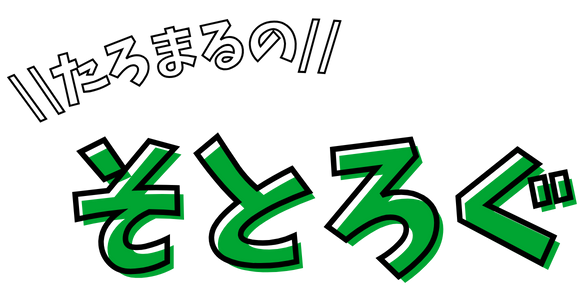
コメント